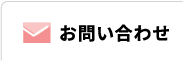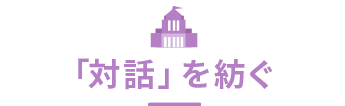課題ピックアップ
どんな立場の人にも、人としての尊厳が守られ、地球環境が持続可能であるためにどのような政治システムが有効であるかという視点で、尾張旭市ならではの環境や特徴を踏まえながら、それぞれの課題と向き合っていきたいと考えています。
いち議員として取り組めること

まずは、自分自身が課題意識をもって調査したり、課題に向き合うことから始めます。
一人の議員として取り組めることは、成果がどれだけ見込めるか
未知数ですが、少なくとも、自身の判断で動けるということは機動力の面で自由です。その点を生かしていきたいと考えています。
会派『市民まちづくりネット』でまとまって取り組めること
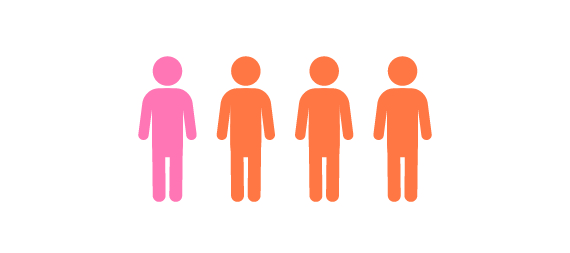
尾張旭市議会定数21人のうち、4人で「市民まちづくりネット」という会派を結成し、議会活動に取り組んでいます。
過半数(11名)の賛同がなければ市を動かすことは難しいですが、議会内のそれぞれの所属する常任委員会での課題を情報共有したり、意見反映するなど、一人では限りがある部分をカヴァーしあえればと願って活動しています。
議会の意志として市政に向き合う

「市」と「議会」が対等な立場に立つことで、意見の公平さを保つ事ができます。
「二元代表制」といい、よく報道で目にする国会運営のように国会議員同士が、 「政府=与党」VS「野党」というように、 向き合うのではなく、 地方議会は、 「市長」VS「議会(議員)」というように、 執行権を持つ市長に対して 議会が提案したり認めたりしていく形で、 議会全体が「野党」の役割です。
「市長与党」や「市長野党」といった分類をする方もおり、議会21人が団結して市の政策に意見を言う機会は多くありません。
課題ごとに重要性を検討し、11名以上最大21名の意志として、市政に向き合う事を目指しています。
ピックアップリスト
-
2024年11月19日
監査委員資料渡し打ち合わせや保護者仲間とMTG
-
2024年11月13日
未来の部活検討会 -中学生の部活動地域移行に向けた指導者確保について
-
2024年11月12日
六市監査委員事務研究会レポート
-
2024年11月07日
愛知県都市監査委員会:休館日の図書館の一室で開催
-
2024年10月31日
総務委員会 行政調査